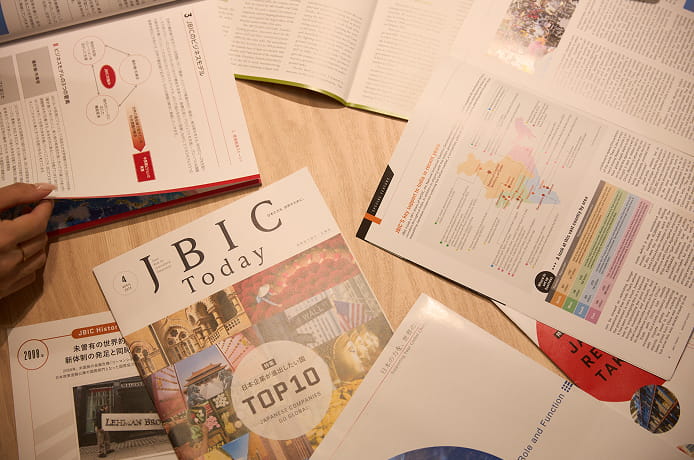語学・金融知識のスキルアップ 座談会
公開日 / 2023年3月1日
語学力や専門知識を習得できる、JBICの恵まれた環境とは
OUTLINE
国際ビジネスの最前線で活躍するJBICの職員には、金融などの専門知識に加え、高度な語学力や交渉術が求められます。そのため、幅広い人材育成制度・研修プログラムが充実しています。義務研修である「英語ウィークリーレッスン」や「財務分析研修」をはじめ、必要に応じて利用できる「業務研修受講補助制度」や「海外留学プログラム」などを、どのように活用しながらスキルを習得しているのでしょうか。職員たちが語り合いました。
PERSON










英語ウィークリーレッスンなど
語学力を養える仕組みがある
藤井JBICでは、業務の中で英語力が求められる場面も多いですよね。皆さんは、どのように習得してきましたか?
中嶋入行1・2年目の全職員が週1~2回受講する「英語ウィークリーレッスン」かな。ネイティブの講師からマンツーマンで学ぶことができました。学生時代に留学などを経験していなかったので、入行後に英語を学べる制度があるのはとても有り難かった。
西宇僕も入行前に海外留学の経験がなく、英語力に不安を抱えていたよ。だから「英語ウィークリーレッスン」はとても心強い研修だった。
中嶋自分が学びたいテーマを選べるのは嬉しい。入行当初は出融資担当部門に所属していて、債権回収や事務手続きについて相手国の方に直接メールで連絡することも多くありました。そこで、私はメールや電話で使用するビジネス英会話のコースを選択。実務でのやり取りを例にしながら、丁寧かつ簡潔な英語で自分の伝えたいことをメールに書くためのポイントを学びました。
西宇入行3年目からは、出融資担当部門に配属されたこともあって、「外国語研修受講補助制度」を利用して英語の通信講座を受講した。不安が残っていたヒアリング力を鍛えることができた。
藤井私も入行3年目になって「英語ウィークリーレッスン」が終了したので、語学学校に毎週通っています。経済に関連する英語スキルを高めるために、オリジナルのプログラムを組んで学んでいますよ。
川本「外国語研修受講補助制度」を利用すれば、業務で必要となったときにフランス語や中国語など様々な言語を学べるのも魅力ですよね。
英語ウィークリー
レッスン
入行1・2年目の全職員が受講する英語の義務研修。業務時間中に最大週2回(各50分)、個々が選んだテーマについて、ネイティブ講師がマンツーマンで指導します。
外国語研修受講
補助制度
語学学校(英語・仏語・中国語・ポルトガル語など)への通学費用を一定額まで補助する制度。


義務研修で一から学ぶから
金融知識はなくても大丈夫
藤井金融・財務などの知識も銀行員には欠かせませんね。
川本学生時代は国際政治を専攻していたので、経済・財務・金融の知識がありませんでした。財務分析の基礎事項を学んだのは、入行1年目の義務研修「財務分析研修」です。そこで身につけた知識は、融資先企業の格付けや資産自己査定を行うときなどに役立ちました。
西宇僕は法学部出身で、もともとマクロ経済や会計などの基礎知識がなかった。「証券アナリスト試験の費用補助制度」を利用して勉強することで、業務にあたる上での土台となる知識を身につけられた上に、証券アナリストの資格も取得。一石二鳥だった。
川本融資契約交渉や相手国政府との面談では、年齢や経験、英語力が全て自分を上回るような方々を相手に、JBICとしての意見を主張していくことが求められます。だから、「業務研修受講補助制度」を利用して通信教育講座を受けて、ファイナンスの知識をもっと伸ばしていきたいです。自らの意志で受けたい研修に対して、受講費用を補助してもらえるのは嬉しいですね。
業務研修受講補助制度
業務上必要な専門知識の習得及び職員の中長期的なキャリア形成の観点から、職員が希望する資格学校、大学院、通信教育等の受講につき、授業料や受講料等の費用を一定額まで補助する制度。
業務中や行内外の研修で
実務に直結する知識を習得
中嶋入行時や出融資担当部門への異動時に受講した「業務実務研修」では、行内の全般的な基礎知識や基本所作について学ぶことができました。また、日頃から行内の規則や金融種類ごとに作成されている事務マニュアル、貸出・回収事務マニュアルなどを読むことでも、業務に必要な知識を身につけられています。
藤井私も、普段の業務の中で知識などを習得できることが多いです。産業投資・貿易部で主にメガバンクからの初期的な案件相談に対応していますが、内規やマニュアル、契約書の中のどこに注目して確認すべきかといった業務スキルは自然と身につきました。
川本僕は売電契約に関して専門的に学ぶために、外部団体主催の「南アフリカでのPower Purchase Agreementに係る研修」に参加しました。講師はオーストラリア人の弁護士で、参加者は全員アフリカ出身の弁護士や官僚。発電プロジェクトの契約書のレビューが素早くできるようになりました。
西宇出融資担当部門の有志で運営されている「海外プロジェクトファイナンス(以下、PF※1)研修」や、金融法務課主催の「契約交渉研修」など、行内にも個々の専門性を伸ばせる研修が充実しているよね。
中嶋今後は、「研修会・講習会受講補助制度」を利用して、業務効率化を図る研修を受講する予定。ペーパーレス化や座席のフリーアドレス化を見据え、今後より一層の業務効率化が求められます。業務職として積極的に業務効率化の提案を行い、周囲をサポートしていきたいです。
業務実務研修
実務を行う上で必要な各種基礎知識や、行内規則などを習得する義務研修。
海外プロジェクト
ファイナンス研修
出融資部門の有志で運営されているプロジェクトファイナンス協議会が主催する研修。PFに精通した弁護士等が講師となり、具体的なPF案件についてマーケット動向を踏まえて解説。海外にも職員を派遣しています。
研修会・講習会受講
補助制度
業務上必要な専門知識の習得のために、外部の機関が行っている研修等を受講した際、その費用を補助する制度。


トレーニー派遣や留学など
海外経験を積める機会も充実
西宇JBICでは、海外経験を積める制度も整っているね。総合職として入行した新人・若手職員は、「海外駐在員事務所トレーニー派遣制度」で世界各地の海外駐在員事務所に約3か月間トレーニーとして派遣される。
藤井私はニューデリー駐在員事務所にトレーニーとして行きました。プロジェクトの現場で活躍する方々の生の声を聞くことで、顧客の熱量や本当のニーズを知ることができたのはとても良い経験でした。加えて、その国でJBICを代表して仕事をするために、相手国のことだけでなく、JBICについても全体的に理解する必要性を感じました。私も将来、海外駐在員として活躍したいと思えました。
川本最近では、キャリアは自分で作るものという意識を強くしています。僕は「海外留学プログラム」を利用して英国のエディンバラ大学に1年間留学し、国際関係論の修士号を取得しました。特に、日本政府が推進する「自由で開かれたインド太平洋」について学んだのですが、日米連携など現在の業務にも活かせる知識を修得できました。
西宇僕も入行8年目の頃、英国・ロンドンビジネススクールに1年半ほど留学してMBA※2を取得した。企業の経営・企業戦略から、ファイナンス、会計、マーケティングまで幅広い知識を得られたよ。何より、銀行員やエンジニアなどバックグラウンドの異なる、様々な国籍の人々とディスカッションをした経験はとても貴重だった。その後の実務において、幅広いステークホルダーと協力・調整しながらプロジェクトを円滑に進めていく上で役立っていると思う。
海外留学プログラム
職員が志向する専門性に応じて、業務に関連する経済学、経営学、公共政策、法律などの知識の習得を目的とした海外の大学院への派遣をしています。
海外駐在員事務所
トレーニー派遣制度
新人・若手総合職の全職員を、海外駐在員事務所に約3か月間トレーニーとして派遣。駐在員の業務を体験しながら、日本の外で実際に何が起こっているのかを肌感覚で感じ取ってもらいます。
※1 プロジェクトファイナンス(PF):プロジェクトに対する融資の返済原資をそのプロジェクトが生み出すキャッシュフローに限定する融資スキームのこと。
※2 MBA(Master of Business Administration):経営学修士。