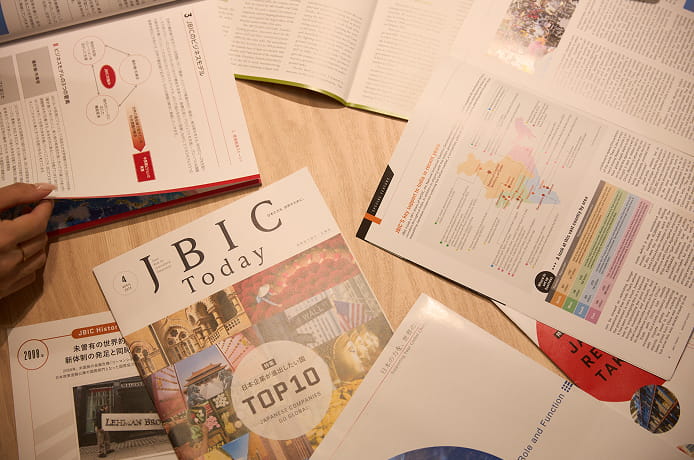人材育成担当特命審議役に聞く:
JBICの人材育成制度
公開日 / 2024年3月1日
新たな研修体系「JBIC Academia」やジョブローテーションが、職員一人ひとりの可能性を広げる
OUTLINE
JBICでは2023年4月、JBICの新たな研修体系「JBIC Academia」が創設されました。入行後の約2か月間で集中的に実施する新人研修「DOJO Program」をはじめ、英語研修、テクニカルスキル研修、海外駐在員事務所トレーニー派遣など充実した研修を設定しています。また、ジョブローテーションを通じて物事を俯瞰する眼を養い、自らの人材価値を高めていくこともできます。職員一人ひとりの可能性を広げる人材育成制度の考え方や特長、今後入行する学生の皆さんに期待することを、人材育成担当特命審議役に聞きました。
PERSON


(当時)
- 1998年
- 海外投資研究所* 総務課
- 1999年
- 開発金融研究所* 国際金融研究グループ
- 2001年
- 国際金融第1部*
- 2003年
- 海外留学(中国)
- 2004年
- 債権管理システム部(現 IT統括・与信事務部)
- 2006年
- 香港駐在員事務所*
- 2008年
- 資源金融部(現 エネルギー・ソリューション部)
- 2010年
- 国際財務部(現 財務部)
- 2012年
- 石油・天然ガス部(現 エネルギー・ソリューション部)
- 2015年
- 原子力・新エネルギー部(現 電力・新エネルギー第1部)
- 2019年
- 審査部
- 2020年
- 財務部
- 2021年
- 人事室
*組織再編により、現在は存在しません。


「JBIC Academia」の研修を通じて
一人ひとりが未来を築く羅針盤に
JBICでは2023年4月より、新たな研修体系として「JBIC Academia」を創設しました。職員一人ひとりが自ら学びたいものを学び、互いに教え合い、そして日本の力で未来を築く「羅針盤」として、それぞれのJBICにおけるキャリアを切り拓き、活躍・成長していく。そうした思いを「Be your own compass」というコンセプトに込め、これまでの研修を3つのFaculty(ヒューマン・コンセプトスキル、テクニカルスキル、グローバルスキル)に再編成しました。
中でも新人研修は、「Door to JBIC Onboarding(DOJO)Program」として全面的にリニューアルしました。JBIC職員に求められるスキル習得を目的とした研修を、入行後の4~6月に集中的に実施。社会人として必要なソフトスキル(ビジネススキル、ビジネスマナー、チームビルディングなど)やハードスキル(金融、出融資、金融法務、財務分析、国際経済など)に加え、各部署に所属している講師による研修を通じてJBICの組織概要や役割、出融資実務についても学びます。
他にも、入行1~2年目職員が業務時間中に週1~2回マンツーマンで教わる英語研修、各部署が随時実施している研修・勉強会で専門的な内容を学べるテクニカルスキル研修など多様な研修を設定しています。特にJBICらしいのが「海外駐在員事務所トレーニー派遣」。総合職の新人・若手職員を、世界18か所ある海外駐在員事務所のいずれかに3か月間派遣します。国際ビジネスの最先端を経験することができ、異文化や多様性を受容する意識、グローバルマインドセットを高める機会にもなることでしょう。


JBIC全体を俯瞰する眼が
自身の強みを最大化させる
JBICの役割は、「日本」と「世界」の国々の懸け橋となり、日本企業による国際「ビジネス」の最前線と日本政府・外国政府による「政策」実現をつなぐことにあり、そのクロスロードの中心が活躍の舞台となります。他の企業とは異なる独自の舞台で、クロスロードを囲む様々なステークホルダーと協働しながら、日本と国際経済社会の発展を見据えて付加価値を共創していくことが求められています。こうした役割を果たすためには、職員一人ひとりが「金融の専門性」や「多面的なスキル」を土台に、「俯瞰する眼」や「大局的な視座」を身につけ、JBICという組織を代表しているという意識を持ってリーダーシップを発揮していくことが重要になります。
これらを養成するための仕組みの一つが「ジョブローテーション」です。ジョブローテーションというと、ジェネラリストを育成するためのものと誤解をされがちですが、狙いは別にあります。JBICは前身である日本輸出入銀行の時代から、政策金融機関として極力スリムな組織体制で最大限の貢献ができるよう、比較的少数の職員で業務を遂行してきました。こうした少人数組織に必要なのは、一人ひとりが自身の強みとなる専門性を伸ばしながら、組織の全体像を理解し、その強みや課題、今後あるべき姿などを考えて活躍することです。幅広い裁量と大きな責任を伴うこの環境こそが、JBICで働く醍醐味であり、職員の成長を加速させてくれます。
そこで、総合職のジョブローテーションでは、職員個々の強みや適性に着目して、「業務分野認定制度」により専門性の軸を持ちつつ様々な経験を積みながら人材価値を高めていきます。多様な経験の中から何かきらりと光る自身の武器を見つけ、磨きあげていくことができます。同時に、様々な部署を経験することによって異なる立場や観点からの捉え方や多面的スキルを獲得していきます。自身の内に多様性を持つことは、柔軟な思考の土台となり、ビジネスパーソンとしての価値を高めてくれることでしょう。こうして物事を俯瞰する眼を養いつつ、職員一人ひとりが突出したリーダーシップを発揮することを目指しています。ジョブローテーションによって培われた多様な「個の力」は、組み合わせることで組織としての強さや価値創造にもつながります。
私自身、バック部門の債権管理システム部(当時)を経験したことが成長の礎になりました。資金の流れなど銀行員としての基礎を学び、金融の種類・手法ごとの融資契約書の建付けや融資商業条件の違いなどを網羅的に理解。これらの知識は、その後に配属されたフロント部門で大いに役立ち、多様な関係者が参加する融資契約交渉の場において臨機応変に落としどころを探り、交渉を主導することができました。様々な経験をすることで自身の価値を高め、JBICを代表する意識を持ってリーダーシップを発揮できた一つの例といえるでしょう。
一方、業務職においては、比較的長い期間一部署に所属することで、OFFJTの各種研修やOJTを通じて業務知識を広く深く蓄積し、「高度な事務のプロフェッショナル」となってもらうことを目指しています。
JBICは、キャリアディベロップメントの取組みにも注力しています。職員一人ひとりのキャリア開発を支援するために、組織と職員の間で定期的な協議を実施しています。また、それぞれの強みや適性を活かしながらジョブローテーションを通じて組織としてどのように人材開発を行っていくかを、職員一人ひとりに対して検討し本人にも共有する機会を、職種を問わず設けています。職員一人ひとりに寄り添いサポートするこれらの仕組みも、少人数組織であるJBICならではの特長だと思います。
近年、経営の考え方として、人材を人件費のかかるコストと捉えるのではなく、組織の成長につながる重要な資本と捉える「人的資本経営」の概念が広がってきました。JBICはこの言葉がクローズアップされる以前から、人材の価値を最大限に引き出すことを常に大切にしてきました。長年にわたり積み重ねてきたこうした思いが、以上のような研修や人材育成の取組みに現れているのだと思います。


熱い思いと行動力を持って
日本と世界の社会課題に挑もう
世界経済は急速に変転しており、産業も日々生まれ変わっています。こうした変革の時代においては、環境変化に後追いで対応するのではなく、様々に飛び交う情報の中からアンテナ高く必要な情報を掴み、何が課題かを炙り出し、自分なりのソリューション(付加価値)を提供していくことが求められます。変化を自ら先取りしていく力を身につけることが、より大切になってくるのではないでしょうか。今後入行する皆さんには、様々な経験を通じて常に視野広く学び続けることで、自身の可能性をしなやかにアップデートしていってほしいです。
また、失敗を恐れ過ぎず行動に移すことも重要です。多様な関係者を取りまとめながら複雑な社会課題に立ち向かっていくJBICの業務においては、頭の中でどれだけ考えたところで正解が出ない場合が多いものです。「行動しながら正解を見つけ出す」という意識で、持ち前の行動力をぜひ発揮してほしいと思います。
そして何より、日頃から自分なりに関心の幅を広げつつ、JBICを通じてどのような社会課題に取り組みたいのかを自問してみてもらいたいと思います。「クロスロードの中心」という唯一無二の立ち位置で、世の中の変化や国際的な動向を俯瞰しながら、ファイナンスを通じて日本と世界の社会課題に取り組めることこそが、JBICで働く醍醐味。「国際ビジネスの最前線で、日本と世界の未来を切り開いていこう」という熱い思いを持ち続けることで、きっと大きなやりがいを持って様々な業務に挑戦していけるはずです。