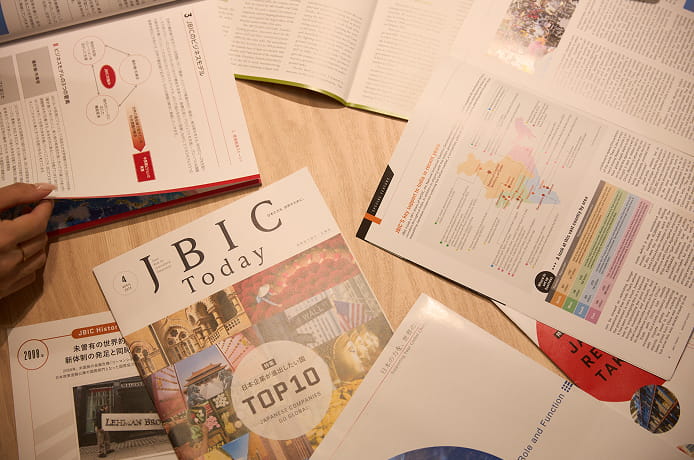新人研修「DOJO Program」
座談会
公開日 / 2024年3月1日
業務に必要な知識・スキルを、入行直後に集中的に学べる研修プログラムとは
OUTLINE
新人職員のオンボーディングを目的として、入行1年目の4月から約2か月間集中的に行う研修プログラム「Door to JBIC Onboarding(DOJO)Program」。入行後早期に第一線で活躍するための助走期間として、ソフトスキルからハードスキルまで基礎的・専門的な知識の習得を目指しています。実際の業務に直結した金融・経済・法務などの研修内容や、グループワークを多く盛り込んだ双方向の学びとは。DOJO Programを企画した職員と、受講した新人職員たちが語り合いました。
PERSON










金融・法務などの知識を
入行直後に集中的に学べる
塩見「Door to JBIC Onboarding(DOJO)Program」(以下、DOJO Program)は、新人職員のオンボーディングを目的として、入行1年目の4月~6月中旬に集中的に行う研修プログラムです。ビジネスマナーやビジネススキルといったソフトスキルから財務分析・金融法務・出融資・語学といったハードスキルまで基礎的な知識の習得に加え、JBICの組織や業務に関する専門的な知識の習得を目指しています。
木村DOJO Programは、2023年に新たな研修体系「JBIC Academia」が創設された際、新人職員やキャリア採用職員向けに作られたと聞きました。どのような意図で研修プログラムを改良したのですか?
塩見入行後早期に第一線で活躍してもらうための助走期間として、まさに道場のような形で集中的にトレーニングを行いたいと考えました。また、JBICの業務内容も時代に合わせて大きく変わってきている中、その期間や内容、時間配分から全面的にリニューアル。今後現場で知識・スキルを活用できる実践的なプログラムとするため、例えば金融スキームの研修などでは実際に業務で携わっている各部署の職員に講義を担当してもらい、リアルな内容や最新のトピックスにも触れてもらいました。
山崎「投資金融」について学ぶ研修では、私が所属している産業投資・貿易部の先輩が講義をしてくださいました。融資形態や金利決定方法などを教わった上で、同部の既往案件を例にした演習にも取り組みました。
渡邉私が所属している船舶・航空部では船舶の輸出案件が多く、借入人は日本製品を輸入する海外の顧客です。「輸出金融」の研修では、海外の顧客に融資することがどのように日本の裨益につながるのかを理解できました。もともと「日本の経済活性化に貢献したい」と考えていたので、日々の業務にやりがいを感じられるようになりました。
山崎金融法務については「融資契約書基礎」の研修で学びました。融資契約書(以下、L/A)を取り扱う上で必要な法律の知識を、実際のL/Aを見ながら教わりました。初めは情報量の多さに圧倒されましたが、出融資担当部門では私たち業務職がL/Aを見ながらシステムへの情報登録や貸出回収事務を担うため、早めに慣れることができて良かったです。
渡邉L/Aと並んで重要な書類が、融資契約締結に必要な承諾稟議です。「案件紹介」の研修では、これらの書類をもとにJBICが行っている融資案件の概要を学びました。最終的な成果物ともいえるL/Aや承諾稟議について知ることで、過去案件を参考にしたい場合に効率的に欲しい情報を引き出せるようになりました。


アウトプットの場も設けて
双方向の研修プログラムに
木村入行時に不安を感じていた経済に関する知識不足は、初めに新人全員が受講する「国際経済(基礎)」で埋めることができました。短期間で体系的に知識をインプットできたので、マクロ経済の知識が求められる外国審査部の業務にも活かせました。
渡邉大学レベルのマクロ経済学を学びましたね。学生時代に経済学を勉強した身としては膨大な学習量をわずか2日間に凝縮していることに驚きましたが、単元ごとに問題が課されて班ごとにアウトプットをするフェーズがあったのでスムーズに理解を深められました。
塩見グループワークや発表などのアウトプットの場も研修の中にたくさん盛り込み、一方的な講義だけに留まらず双方向のプログラムとなるように工夫しました。
山崎業務職を対象とした「出張申請」に関する研修でも、実機を用いてアウトプットをしながら教わりました。OJT開始後すぐにユニット内の担当者がエジプト出張に行くことになり、研修で学んだことが業務に直結しました。
木村グループワークで印象的だったのは、レゴブロックを使った「チームビルディング研修」。新人が持っている課題意識や将来的なビジョンをそれぞれレゴ作品として具象化したあと、個々の作品のエッセンスを組み合わせてチームごとに一つの作品を完成させました。私は、世界各国が保護主義に傾いている現状に対して「世界の一体化を進めるグローバリズムの大切さや、その中での日本の役割の大きさを再認識しなければならない」という課題意識を作品化。その後、チームメンバー一人ひとりの思いを理解し合って、集団的な一つのビジョンに落とし込んでいきました。
渡邊自身の思いを文字で表現すると、ありきたりな文章になってしまいがちです。しかし、頭で考えすぎずレゴを組み立ててみると、潜在的に考えていることまで形として表現できました。
山崎チームメンバーの作品を見ながら話を聞くと、その方が本質的にどのようなことを考えているのかが見えてきました。実際の現場でも、表面的な言葉ではなく、相手の本質的な考えを見極める必要があるのだと考えさせられました。


役員や職員との交流会で
JBICの組織・人を理解
塩見業務知識だけに留まらず、JBICの組織や人についても理解を深めてもらえるよう、DOJO Programでは役員や中堅職員、若手職員との交流会も複数回実施しました。
木村実際に様々なライフイベントを迎えている中堅職員の方々からワーク・ライフ・バランスに関するお話を聞けたのは、将来的なキャリアプランを設計していく上でたいへん参考になりました。
山崎何でも相談できる「インクルーシブ推進オフィサー」(通称「IO」)※という役割を持つ職員とお話する機会がありました。私は、一般的な意味とは異なる使い方がされるJBIC用語について質問しました。例えば、「頭出し」という言葉は、後々発生しうる依頼事項について事前にお伝えしておくという意味で使われているそうです。
渡邉役員交流会で、日印関係など視座の高いお話から、好きなお酒などカジュアルなお話まで伺えたことも貴重な経験でした。特に「若いうちから一つひとつの業務に対して疑問を持ち、それを解消していってください」という言葉が印象的でした。業務中に作成する書類一つとっても、それがなぜ必要なのかと疑問を持つことで、完成度が高まるだけでなく、目の前の作業にやりがいや意義を感じられるようになると気付かされました。
塩見DOJO Programでは、積極的に学ぼうとする皆さんの姿勢が見られて嬉しかったです。JBICでは新人向けばかりでなく、各自の経験に合った学びの機会を継続的に提供しています。今後も、職員一人ひとりの自律的なキャリア形成につながるよう、また組織全体の能力開発につながるよう、世の中のニーズに合わせた幅広い研修プログラムを企画・実施していきたいと思います。
※ インクルーシブ推進オフィサー(通称「IO」)制度:業務・キャリア・組織文化・人間関係など、職場での多様な悩みや疑問を職員間で相談し助け合うための施策として、非管理職の職員などを相談役として設置。