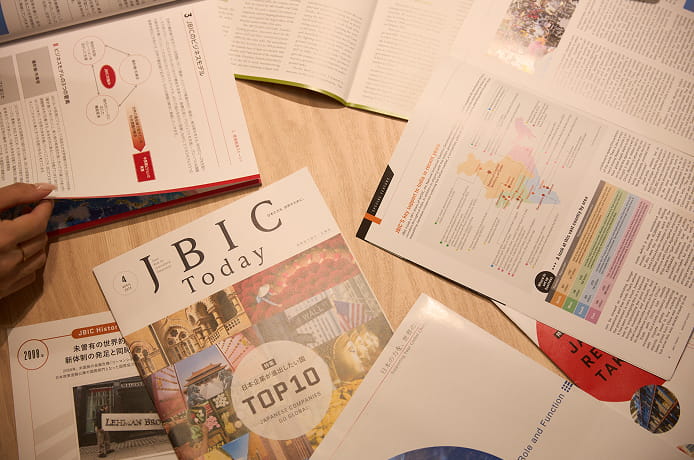ミドル・バック部門で得た俯瞰的な視点が、フロント部門での活躍を後押し
公開日 / 2024年3月1日
入行17年目(エクイティ・インベストメント部・次長)職員のJBICライフとは
OUTLINE
出資業務を担うエクイティ・インベストメント部に所属し、次長 兼 スタートアップ・イノベーション推進企画ユニット長として活躍している若月智愛。今までのキャリアを振り返ったとき、ジョブローテーションを通じて、フロント部門では担当分野の専門知識などを、ミドル・バック部門では組織全体を俯瞰する力などが養われたといいます。各部署で得られた成長や、JBIC職員にとって大切な姿勢・資質、育児と仕事を両立して働く日々について聞きました。
PERSON


- 2007年
- 審査部
- 2009年
- 産業投資・貿易部
- 2010年
- 船舶・航空部
- 2014年
- 財務部
- 2017年
- 船舶・航空部
- 2020年
- リスク管理部
- 2023年
- エクイティ・インベストメント部


ミドル・バック部門を経験し
組織全体を俯瞰する力を獲得
私は現在、出資業務を担うエクイティ・インベストメント部に所属し、次長として部門全体の企画調整業務を行っています。また、2023年の株式会社国際協力銀行法改正に伴い、海外事業を行う国内のスタートアップへの出資業務にも注力していく中、スタートアップ・イノベーション推進企画ユニットでスタートアップ向け出資の取組体制などを検討しています。
今までのキャリアを振り返れば、長く所属していたのは船舶・航空部でした。船舶業界と航空業界では、支援する手段が異なっています。船舶業界では日本で建造された船舶を海外に輸出する際に輸出金融を用いて支援し、航空業界ではボーイングやエアバスの航空機を日本のエアラインが輸入する際に輸入金融を用いて支援します。また、海外でFPSO(浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備)を運営する日本のオペレーターを支援する案件ではプロジェクトファイナンス※が主に取り扱われていたので、同部ではJBICの金融商品を幅広く学ぶことができました。
仕事をする上で必要な一般的な知識については、通信教育や書籍、行内外の研修でも習得できたのですが、振り返ってみると成長に最もつながったのは案件を通じた学びでした。船舶・航空分野の関係者はその道のプロであることが多く、彼らと渡り合うためには高度な専門知識を短期間で身につける必要がありました。それが良いプレッシャーとなり、成長を加速させてくれたように思います。産業投資・貿易部と船舶・航空部では、リーマンショック時の危機対応も経験しました。JBICが政策金融機関としてマーケットと逆行して資金提供を行い、日本企業を支援するところを目の当たりにし、その役割の重要性を強く認識することができました。
こうしてフロント部門で着実に成長することができましたが、飛躍的な成長を実感したのは、むしろミドル・バック部門時代でした。審査部ではJBICがどのようなリスクであれば積極的に取りにいくのか、財務部では送金手続き・資金繰りなどJBICの出融資業務に欠かせない事務を理解。後にフロント部門に配属された際、審査調書を適切にまとめられたり、資金移動がある場合などに前もって連絡するなど組織全体がスムーズに回るよう配慮できたりと、各部署の経験が大いに役立ちました。また、リスク管理部ではJBICのポートフォリオ全体を管理する中で、例えばどのような業種・地域・金融商品の比率が高いかなどを把握できました。このようにミドル・バック部門を経験することで、プロジェクトを支える資金調達や案件管理などへの理解が深まり、組織全体を俯瞰する力が養われました。


自ら学ぶ姿勢を大切に
自分を信じて未来に挑もう
JBIC職員は異動のたびに短期間で専門知識を身につけるトレーニングを積みますし、膨大な過去の事例からも業務に必要な知識・スキルを学ぶことができます。しかし、必ずしも外部から専門的な知識を求められないユニークな組織でもあるため、自ら学ぼうとする意識を持ち続けなければ、行内調整のみに長けた人材にもなりかねません。そこで私は、世の中の一般的なやり方を学んでから、JBICのやり方を習得するように日頃から心掛けています。また、セミナー・カンファレンスのスピーカーやパネリストの依頼があった際には、自分自身を追い込むため積極的に引き受けるようにしています。
行内でも輝かしい活躍をされている方々には、決まって忍耐力があると感じています。何か新しいことにチャレンジする際は、相応の反発があるものです。それでも諦めることなく、丁寧に粘り強く関係者の理解を得つつ遂行していく忍耐強さは、JBIC職員にとって重要な資質の一つだと思います。また、多面的に物事を見ること、相手の立場に立って物事を考えること、その上で優先順位付けができることも大切。民間金融機関での勤務経験がある私は、行内に限らず、行外の関係者の気持ちも想像しながら仕事をするようにしています。
学生の皆さんには、自分にとって譲れない価値観であれば決して譲らないでほしいし、譲らないですむ組織を選んでほしいと思います。謙虚でいることも大切ですが、これまでの人生で培ってきた自分の価値観、自分の能力をもう少し信じても良いのではないでしょうか。スタートアップを支援する業務に携わっていると、若い方々が第一線で活躍されています。中にはメタバースなど、若者の価値観でなければ理解しづらいビジネスもあります。これからの時代を担う皆さんが、自分を信じて、自由な発想で、明るい未来を作っていってくれることを期待しています。


育児を通じて再認識できた
チームで仕事をする重要性
子供が産まれてから、周囲との関わり方が変わってきました。もともと自分で全てをやろうとしていた私も、育児によって時間の制約が生まれ、周囲を頼るようになりました。すると、自分一人でやっていたときよりもずっと大きな成果を出すことができ、チームで仕事をする重要性を再認識できました。また、子供が1歳半くらいになると「自分でやりたい」と言うことが多くなり、人間は本質的に承認欲求が強いのだと気付かされました。それからは相手を尊重し、何かをしてくれた際は必ずお礼を言うようにしています。
子供が幼稚園に入園した頃のこと。私は「昼過ぎにお迎えに行き、託児所に預けてから仕事に戻りたい」と考えていました。しかし、当時は昼休み以外に仕事を抜けることができず、育児と仕事の両立に悩まされていました。そんなとき、人事室に相談したところ、勤務時間の短縮(時短)を朝と夕方の時間帯以外にも使える制度を整えてくださり、とても助かりました。近年では育児・介護との両立支援制度もどんどん充実してきており、プライベートとの両立を図りやすい職場になってきています。今では、子供が夕方には小学校から帰ってくるので、夫と交代で16時頃からテレワークをするようになりました。
趣味のピアノで子供が弾くヴァイオリンの伴奏をしたり、学校の出来事などを子供とおしゃべりしたりするのが、私にとって何よりの癒やしになっています。今後は、伴奏をより上手にできるよう、ピアノの本格的なレッスンを受けてみたいです。また、子供と一緒に、ロバート・サブダのような「飛び出す絵本」を作ってみたいとも考えています。
※ プロジェクトファイナンス(PF):プロジェクトに対する融資の返済原資をそのプロジェクトが生み出すキャッシュフローに限定する融資スキームのこと。